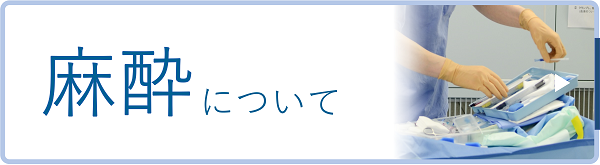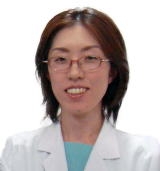麻酔について
麻酔について詳しく紹介しています。
麻酔紹介動画
「全身麻酔で手術を受けられる方へ」
「脊髄くも膜下麻酔・硬膜外麻酔で手術を受けられる方へ」
「局所麻酔で手術を受けられる方へ」
概要
手術・外傷・感染・痛みなどの様々なストレスから患者さまを守る専門の診療科です。
麻酔科は手術・外傷・感染・痛みなどの様々なストレスから患者さまを守ることを専門とした診療科です。
麻酔には、大きく分けて「全身麻酔」と「区域麻酔」があり、患者さまの疾患に最も適した麻酔方法を選択しています。また、手術中は患者さまの状態を常に把握し、秒単位の変化に応じて患者さまの生命を守っています。
手術中の麻酔管理のみならず、集中治療科との連携のもと、集中治療室における重症患者さまの周術期管理も行いながら、より質の高い医療を提供しています。
麻酔には、大きく分けて「全身麻酔」と「区域麻酔」があり、患者さまの疾患に最も適した麻酔方法を選択しています。また、手術中は患者さまの状態を常に把握し、秒単位の変化に応じて患者さまの生命を守っています。
手術中の麻酔管理のみならず、集中治療科との連携のもと、集中治療室における重症患者さまの周術期管理も行いながら、より質の高い医療を提供しています。

特色
尾張西部地区でも多数の麻酔科専門医が常勤
私たち麻酔科医は、患者さまと接する機会が多くはありません。しかし患者さまに一日でも早く笑顔を取り戻していただきたいという気持ちは誰よりも強く持っています。これを実践すべく、最新の知識の習得や最先端の医療機器の導入はもちろん、患者さまとご家族お一人おひとりの心のケアにも着目し、地域の皆様が安心して手術や麻酔を受けていただける環境づくりを目指しています。
また、日本麻酔科学会の定める、麻酔科専門医8名が常勤し、24時間365日様々な緊急事態に対応できる体制を整えており、周術期管理のプロフェッショナルとしてより質の高い医療を提供できるよう努めております。
また、日本麻酔科学会の定める、麻酔科専門医8名が常勤し、24時間365日様々な緊急事態に対応できる体制を整えており、周術期管理のプロフェッショナルとしてより質の高い医療を提供できるよう努めております。
臨床研修医・救急救命士の実習について
当院は、臨床研修医指定病院のため、研修医が指導医とともに患者さまの麻酔に関する医療行為を実施することがあります。また国の方針に基づいて、救急救命士の実習を行う場合もあります。救急救命士の実習に関しては、患者さまに事前に十分説明したうえで「救急救命士の実習にかかわる同意書」にご署名をいただいています。
どちらも熟練した専門医の監視のもとで行うため、患者さまに不利益をもたらす恐れは一切ございません。また、もし患者さまが実習の実施を拒否されても、その後の治療にはなんら不利益を生じません。
どちらも熟練した専門医の監視のもとで行うため、患者さまに不利益をもたらす恐れは一切ございません。また、もし患者さまが実習の実施を拒否されても、その後の治療にはなんら不利益を生じません。
お知らせ
臨床研究へのご協力をお願いします
麻酔科では、下記の臨床研究を行っています。
1.人工膝関節置換術における膝窩神経叢ブロックとIPACKブロックの術後足関節運動筋力のランダム化比較試験 (PDF)
(承認番号:2023-023 研究責任者・連絡先 麻酔科 酒井規広)
1.人工膝関節置換術における膝窩神経叢ブロックとIPACKブロックの術後足関節運動筋力のランダム化比較試験 (PDF)
(承認番号:2023-023 研究責任者・連絡先 麻酔科 酒井規広)